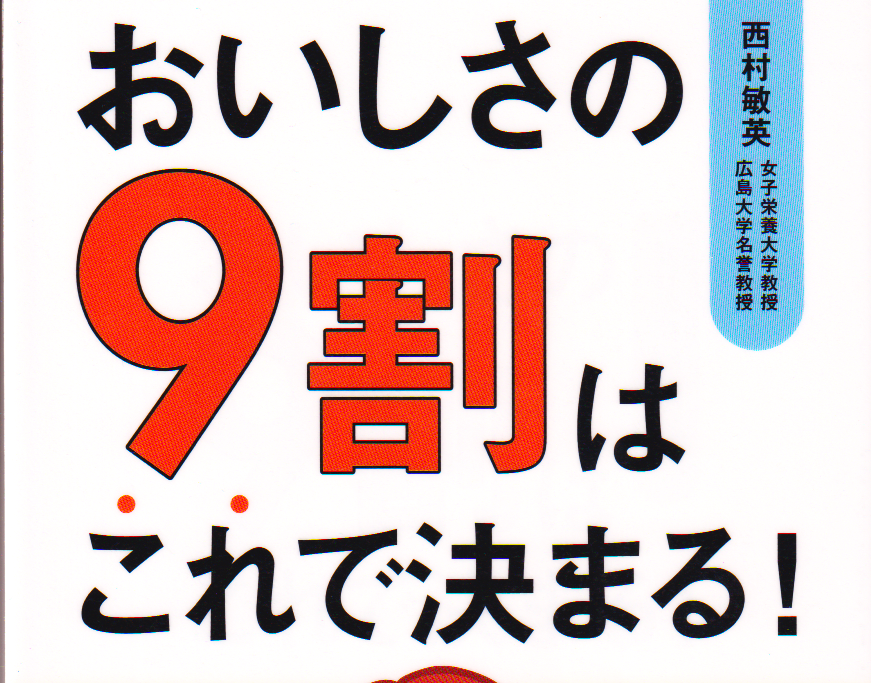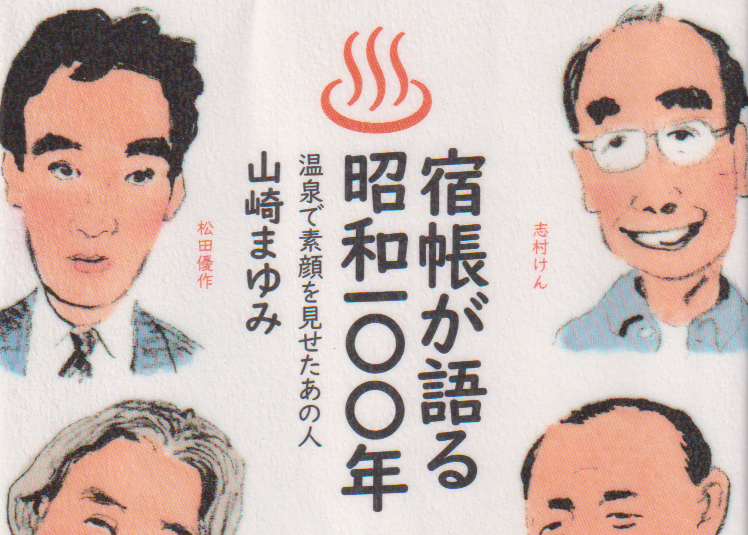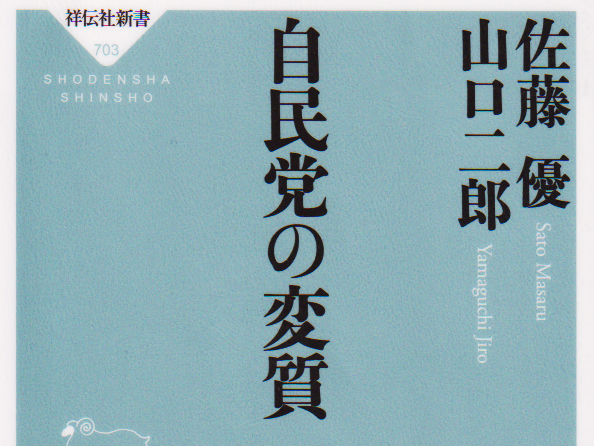この時期になると自然に思い出す言葉ですが、一月は往(い)ぬる、二月は逃げる、三月は去る、四月は新年度―まったく「歳月人を待たず」だなぁ、と嘆息。
そして、「もし今日が人生最後の日だとしたら、今日やることは本当にしたいことなのだろうか?」というジョブズ氏の言葉が年を重ねるごとに、なんとも切なく胸に刺さりますが…。
◆『おいしさの9割はこれで決まる!』(西村敏英、女子栄養大学出版部、2024) 著者は女子栄養大学教授、広島大学名誉教授
一日二回の食事から三回食へと、一般庶民にまで広がったのは江戸時代だそうですが、美味しく食べられるに越したことはないですよね。ですが、一日三回も用意する食事、正直、面倒くさいです。美味しい食べ物をサッと安上がりで作るコツを知りたいとタイトルに引かれて読んでみました。
そもそも「おいしさ」とは何かが気になります。本書は、「おいしい食べ物とは何か?」の問いから、「香りと味わい」の関係、「食品科学がおいしさをアップ」させる、煮る・焼くなど作る「プロセス」というように、テーマごとに論点が整理されています。カラー刷りのイラスト・図表・写真も豊富で視覚的にも理解しやすい。「おいしさ」は味だけでなく色どりや見た目、雰囲気なども大切で、味がイマイチなら素材の色や匂いでもカバーできることがよく分かります。
私の料理の基本は、とても簡素です。主食は無洗米を中心に、ときにパン・うどん・お餅を取り入れ、おかずは「野菜とタンパク質(肉・魚・卵)」のバランスを重視してつくり、お汁(あるいは豆乳・牛乳)を添えるのが定番。出汁は「千代の一番」がイチバン気に入っています。
さらに「簡単・美味しい・飽きない」を追求したいです。
それにしても、お米の値段は高止まりのまま。長年の「減反政策」のツケがとうとう回ってきました。頭が痛いですが、これは上がっても下がらない構造型の「価格革命」というしかありません。
これに対し、野菜・魚などの「生鮮食品」は、本来、収穫量に応じて上がったり下がったりの短期の「価格変動」を繰り返す性質がありますが、日銀のあまりにも極端な「金融緩和策」の長期固定(=無策とも言えます)」と超円安(の放置)では、今後も上がり続けてインフレに転化するおそれがあります。
近くのスーパーで買った時の手元のメモ帳を見ると、キャベツ(ひと玉、税込み)は、149円(昨年2月2日)から322円(今年2月1日)と2.2倍になっています。モヤシだけは、ず~っと31円でがんばってくれていますが、、、。
また、「医食同源」―年齢とともに気になるのが血圧。私は150を「上限」の目安(OMRONの手首式で測定)にして、できる限り「減塩」と「運動」(毎日、ひたすら散歩)に努めています。血圧計の数値を横目に「降圧剤」に頼らなくて済む食事を続けたい、と思っています。
◎「イゴノミクスの世界」格言と法則
・「不得貪勝」(むさぼり勝とうとしてはならない)。
・同様に、むさぼり食べようとしてはならない!食は美味しく控えめに。