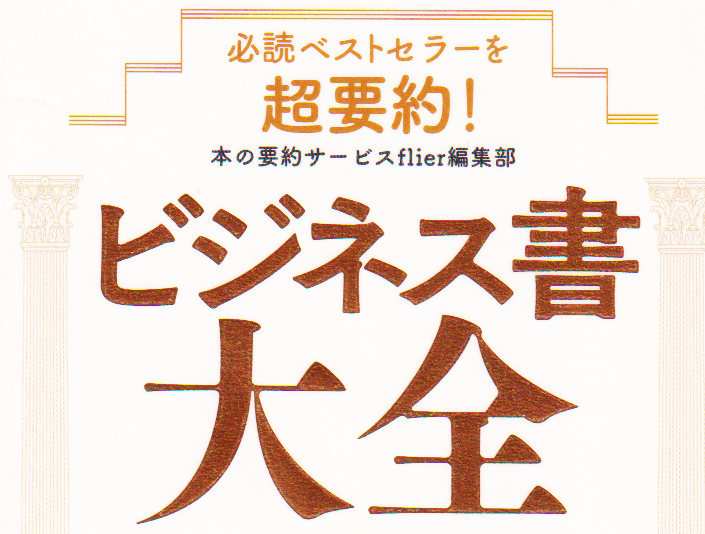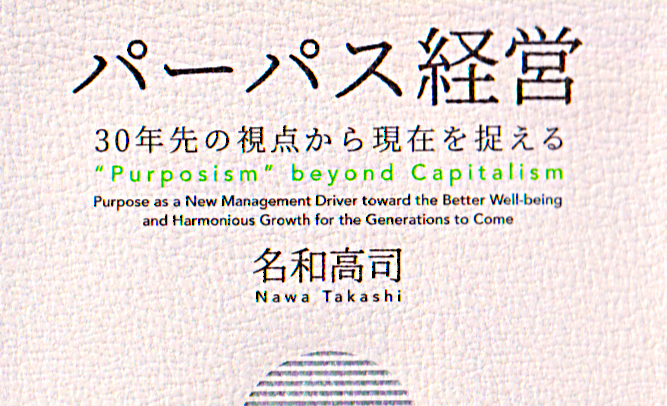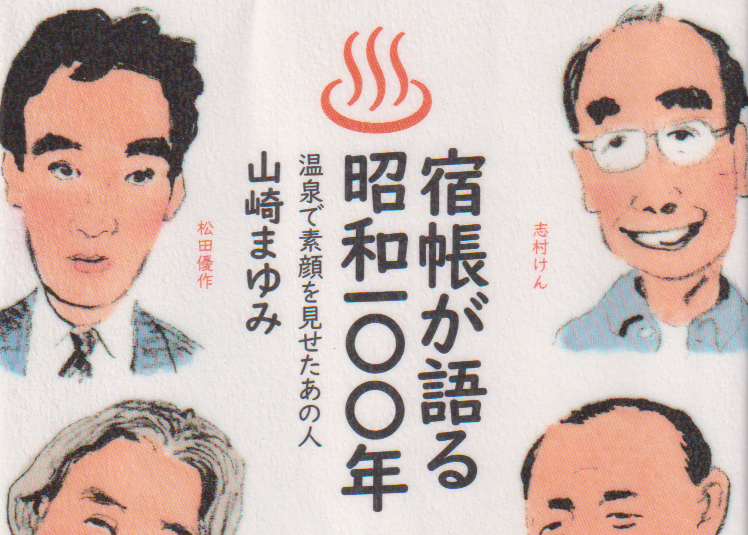明けましておめでとうございます。
旧年中は、多くの皆さまに本ブログをご覧いただき、誠にありがとうございました。
本年は巳年にあたり、古い殻を脱ぎ捨て斬新な視点を提供できるよう努力してまいりたいと思います。
皆さまのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
1「一望百冊」の本
『必読ベストセラーを超要約!ビジネス書大全 一生モノの仕事力が身につく名著100冊を1冊にまとめてみた』(本の要約サービスflier編集部著、新潮社、2024)
100冊もの本をなんと1冊(431ページ)に凝縮!『孫子』のような「大古典」から今日注目の書までを網羅。しかも章別構成は「コミュニケーション」から日頃の「習慣」「仕事・勉強術」「お金」に「健康・メンタル」など7つにカテゴライズされ、各書籍の核心を分かりやすく紹介しています。
本書は、読者のライフスタイルや関心に応じたさまざまな活用の仕方がありそうです。ビジネスだけでなく、いわば生活全般を「ブラッシュアップ」する上で大いに役立つのではと思います。
2 気になる高止まりの米価
『米ビジネス』(芦垣裕、クロスメディア・パブリッシング、2024) 著者は有限会社初音屋 代表取締役、米・食味鑑定士/水田環境鑑定士/調理炊飯鑑定士/おこめアドバイザー
昨年は「令和の米騒動」のニュースが話題となりました。なぜか騒動後もお米の値段は高止まりしています。著者は「日本人の生活はお米を知ると豊かになる」との思いから、お米の品種や有機農法、無洗米や精米技術、お米の流通・小売り、さらには最新の炊飯器・炊き方、外食とお弁当、そして海外事情に至るまで分かりやすく解説しています。
本書は、お米について一から学べる入門書となっており、米価高止まりの背景を考えるうえで参考になります。
3 近代文明を語る鉄道史
『日本鉄道廃線史』(小牟田哲彦、中公新書、2024) 著者は日本文藝家協会会員
私は幼少の頃、何度か本物の蒸気機関車に乗せてもらったことがあり、鉄道には特別な親近感と思い出があります。本書は、私にはとても切なくも興味深い鉄道の廃線史であり、とりわけ近代文明を支えてきた鉄道の変遷には「無常の感」を抱かずにはいられません。
著者は、「身の危険」を感じつつも全国の廃線跡を実際に訪れ、地域社会がどのように変わったのか踏み込んで記述しており、本書の価値をいっそう高めています。「地方創生」「地域再生」の時代、今後の公共交通のあり方を考える上で必読の書といって過言ではないでしょう。
4「金利」を通して経済を読む
『なぜ日本の金利は常に米国より低いのか―131のステップで誰でもできる金利予想の教科書』(角川総一、ビジネス教育出版社、2022) 著者は「(株)金融データシステム」代表取締役
ようやく「金利のある世界」に戻ってきた日本。著者は「金利を学ぶなら今でしょ!」のフレーズのもと、金利の役割を初心者にも理解できるように、図解も交えながら解説しています。
本書は、金利の変化を考慮することの重要性を説いています。日銀の金融政策はどうなるのか。対米関係では為替相場も気になります。円安はこのまま続くのか、株高はどうなるのか。金利を切り口にして経済問題を読み解くために、最適のテキストとして、ぜひおすすめしたい一冊です。
5「異分野結合」の『イゴノミクス(Igonomics)の世界』へ
『呉清源 二十一世紀の打ち方』(呉清源、NHK出版、1997) 著者は中国福建省出身(1914‐2014)、日本棋院名誉客員棋士
本書は、21世紀における囲碁の新しい打ち方を提起したものです。呉清源(ごせいげん)氏といえば、「昭和の棋聖」「漂泊の天才棋士」などと称され、囲碁界に「中央重視」の革命的な新風を巻き起こしました。さらに、21世紀に向けて「囲碁は調和である」という観点から、一手一手が「全局面と調和する」新たな布石について展望しています。
私は本書から「中庸」(共存・協生)の大切さを学び、囲碁と経済という「異分野」の結合を構想し『イゴノミクスの世界』(Igonomics)を2019年に出版しました。
また、お正月の1月5日(囲碁の日)、インターネット碁で「囲碁の打ち初め」を行い、新春の対局を楽しみました!今年は体調も回復してきましたので、春になり暖かくなったら、近くの「囲碁センター」に出かけてみたいと思っています。
※「医食同源」は身体の栄養、「医〈書〉同源」は心の栄養かなと思います。