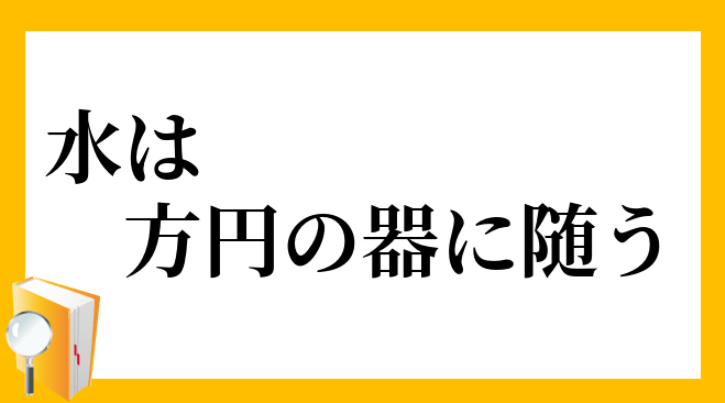◎「イゴノミクスの世界」格言と法則
・囲碁では「死んだ石」と「死んだふりの石」が現れ、対局者を惑わす!
―「死せるマルクスが現代人を走らす」ことも、「現代人が死せるマルクスを走らす」こともある。どちらも世界を暗闇に陥れる。死せる者は、決して蘇らせてはならない。
・結論から言えば、資本主義は〈水〉のように「方円(ほうえん)の器(うつわ)に随う(=従う)」性質があり、どんな社会環境にも適応していくと思われる。(「方」は四角い碁盤・「円」は丸い碁石、「方円」とは囲碁の美称。拙著『イゴノミクスの世界』p.29参照)
◆「コミュニズム神話」―「第三の道」について
⑥ あの「社会主義」は何だったんだ!―人類の世界史的教訓
(ゼミ長) 『人新世の「資本論」』の検討、11回目、先生、お願いしま~す。
は~い(^▽^)/ この検討の最終回。では、斎藤説が生まれた背景みたいなんから始めようか。これは、ぼくが本で読んだり人から聞いたことなんだけどね――
❶「ソ連や中国はマルクス主義を捻じ曲げた。ソ連はスターリン主義の独裁だった、中国は毛沢東の個人崇拝があった」。
❷「指導者の誤りがなければ、本物の社会主義へ行けた。あれはニセモノ社会主義だった、また革命やればいい」、と。
でも、本当にそうだろうか?
ぼくはね、ソ連も中国も「指導者」たちは、マルクスがその生涯をかけて思い描いた人類平等の「コミュニズム社会」を目指したと思う。
労働者も農民も希望に燃えて頑張ったんだと思う。当時は、世界中の勤労者に明るい夢と希望を与えたんじゃない?でもねぇ――
(ゼミ長) それで、どうなったのですか?
うん、見果てぬ夢に終わった、、、。人類にとって理想の「桃源郷」―そんな「社会主義社会」(コミュニズム)への道は、どんなに探してもなかったんだ。未知の「道なき道」は道にあらず、だった、、、。
それどころか、ソ連で、1950年代、スターリン亡き後、いわゆるフルシチョフ「秘密報告」が公になってさ、スターリン統治下の凄惨な人権蹂躙の内情―1千万人を超えるほどの大量粛清の犠牲者―が明るみに出て、世界中の人々を驚愕させたらしい。
ぼくは、いつか、ある大先輩の先生が研究室で「まさかそんなとは、知らなかった…」淡々とした口調で語るのをじっと聞いた。
小学生の頃、叔父さんがね、抑留された極寒のシベリアで重労働に従事させられ亡くなった、と祖父から聞かされていたので、、、思わず涙が出たよ…。
郷里には命からがら帰還した人が叔父の髪の毛を持ち帰ってくれたらしく、小さな木箱に大切に保管してあったばい。
話を戻して――
「第三の道」として、今日、斎藤さんが「コミュニズム社会」論を提起してくれた。本書は、アカデミズムの世界に生まれた異色の「コミュニズム宣言」の書だけど、やっぱり立ちはだかる「厚い壁」は突破できていないなぁ。
(ゼミ長) どうしてですか?
『資本論』を下敷きにした「資本の論理」とか「資本主義」認識に引きずられると、すでに詳しく検討してきたように――
人によっては〈資本主義の枠内・枠外〉を意識したり、資本主義に続く〈未来社会〉を想定したくなるんだよね。
ぼくの言う三位一体の「資本論神話」・「経済成長神話」・「コミュニズム神話」に、知らず知らずハマっちゃうんだ。
さっきぼくは「厚い壁」と口にした。でも実は「壁」なんか、本当はないんだよ。どういうことかと言うと――
『資本論』は、資本主義の崩壊を予言したけど理論的な証明はできていなかった。「社会主義」(コミュニズム)社会についても、〈商品、貨幣がなく、階級や国家も存在しない社会〉とマルクスは想定、これも思い付きでしかなかったというしかない。
ロシアや中国の革命家たちは、理想と現実の狭間で迷路に入り込んでしまい、かといって「資本主義」へ引き返すこともできず「社会主義社会」を名乗るほかなかったんや。
マルクスは、革命後、資本主義から社会主義へ至る一定の助走期間として「プロレタリアート独裁」(Diktatur des Proletariats)の「過渡期」(Übergangsperiode)がある、と考えていた。
しかし、実際には「共産党指導者」による情け容赦ない独裁政治が行われた、、、。その果てに、たどり着いたのが〈(国家)資本主義〉だった!とは、、、。
かえって、変幻自在な資本主義の〈強靭な生命力〉が実証されたってわけさ。
イゴノミストとして、ぼくらしく言えば、資本主義はどんな社会環境にも、まるで〈水〉のように「方円の器に随う(=従う)」んだね。
この冷厳な事実は、人類の世界史的教訓として謙虚に受け入れるべきや。もう二度、三度と「コミュニズム」に挑戦するなんて、あっちゃいけない。
「コミュニズムの実現」・「資本主義の廃止」は、理論的にも実践的にも、失敗ではなく不可能だってことなんだもん。
マルクスの理想とする「未来社会」は存在しないし、ましてや理想の人間=指導者もこの世にいるはずがない――「マルクス思想」・「コミュニズム論」は、とっくに「オワコン」ですよ。
マルクスの言葉は、21世紀の知性からすると、多く語れば語るほど古臭く時代遅れに聞こえてしまう。
◆ 先ほどの「過渡期」論に関して重大な問題があることにも触れておこう。それは――
❶マルクスは、社会主義に達する高度な生産力を前提しているにもかかわらず、社会主義への準備期間として「過渡期」を想定していた。しかし、それは論理的に成り立たないということ。
❷この過渡期に限定したとはいえ、「プロレタリアートの独裁」を言ったことで、「共産党」や「労働者党」に「独裁政治」のお墨付きを与えた/現に今も与えていること。
これでは、悲しいかな、人間解放の平等な社会はやってくるはずがない。
「指導者」たちが「路線闘争」の名目で野心剥き出しの「権力闘争」に明け暮れ、国民に対しては、理不尽な「力の行使」が「法の秩序」に優先しちゃうよ。
(村上さん) もう『資本論』は読まれなくなるんでしょうか?
あぁ、脱『資本論』かぁ、、、。いや、まだまだ読まれるでしょ。人類に大きな影響を与えた大古典だから。
でもね、マルクスがあぁ言った/こうも言ったとか、解釈し直してみたの類の「訓詁学」には、「トラの威を借る」時代錯誤の匂いがしてならないよ、、、。
◆ 改めて、マルクスの「協同組合」論を確認すると(②―9参照)――
❶「協同組合運動は、階級対立に基礎をおく現代社会を改造する力の一つ」と評しながら、すぐ続けて❷「協同組合は資本主義社会を改造できない。国家権力が資本家から生産者の手に移る変化が必要である」と念を押していたんだよね。(『マルクス・エンゲルス全集』第16巻 p.194、オンラインでも読めます)
斎藤さんは、この❶は引用してる(p.262)けど、❷については引用も言及もしていない。本書は「協同組合」の道を説くので都合が悪いんでしょう。
明治開国から、また『資本論』初版からも、およそ160年が経たちます。
日本には日本らしい文化や歴史、教養の土壌があるし、若い君たちには、外来の〈輸入学問・思想〉を崇拝するのではなく、これらを踏まえて学問や思想を大いに発展させてほしい、心からそう期待してるよ!
(ゼミ長) 斎藤幸平著『人新世の「資本論」』の検討、この11回目で終わりになります。先生、お疲れ様でした!(先生:みんな、長くなったけど、お付き合いありがとう!猛暑や、では、次回)「ピンポーン、パンポーン♪」
画像 「水は方円の器に随う」オンライン・ことわざ辞典